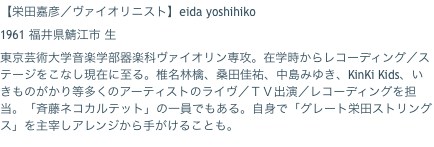 |
||||
 |
||||
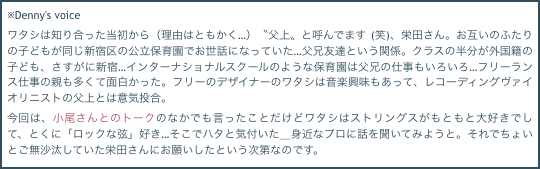 |
||
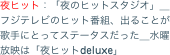 |
||
D(以下Denny):大学が芸大ですよねぇ。芸大でヴァイオリンやってて…卒業の段には進路としてどういう選択肢があったんですか?
E(以下 栄田):在学中から録音の現場でバイトをしていて…とにかく仕事がたくさんあったんですよね、当時は。だから卒業といってもそのままずるずると…。
D:それなりの実入りもあって…。
E:そうそう (笑)。
D:まぁよくあるパターンですか (笑)。でもオーケストラに入るとか音楽教師? …クラシカルな方面という選択は?
E:う〜ん、ポップスというかロックというか、好きで聴いていたというのもあるけれど、とにかく仕事量がね、半端なくあった頃だったから。
D:何でもアリ?
E:そう、演歌からCMから歌番組…なんでも。昔って歌番組が毎日あったんですよ、「生」で。水曜の『夜ヒット』* とか。木曜はロッテ提供の…TBSの番組もやってたかな。テレビ仕事だけでも毎週毎週あったわけだし。
D:生番組の進行はどんな感じなんですか?
E:譜面もらってまず(歌手)本人の歌と合わせて、次に通しのカメラリハーサル…それと本番、三回ですね、基本は。
D:それを、歌手は自分の歌だけだけれど演奏の側は全員分だから大変スなぁ…。
E:『夜ヒット』は本番が9時だったけど「入り」は午後の1時頃だったですかねぇ。
D:まぁ当たり前に当時のヒット曲ばかり…ですよねえ。その譜面を初見で弾かなければならない?
E:それが仕事ですから (笑)。ただリズム隊の人たちは前もってテープでチェックしていたかも…、キーの違いやTVサイズ * とか尺の問題もあるしね。
D:レコーディングに関してはどうでしたか?
E:昔はほぼ同録(同時録音)で、リズム隊の人もストリングスもブラスも一緒の部屋で録ってましたね。いまでも演歌の人たちの録音は同録じゃないかな。その場でキーを変えたりするし。
D:最初の録音の時はトラック数 * はどうでした? まだアナログでしょ?
E:16チャンネルぐらい…だったかなぁ。
D:うち弦の取り分は?
E:2から4トラック程度。なので(マイクは)アンビ * で2本と上から吊っている2本とかを合わせた音を2トラへ入れるとかね。
D:規模というか、弦となると人数が必要ですよねぇ。その数はどうやって決まるわけ?
E:ストリングスの場合、リーダーがいてその人がメンバーを集めているんですよ。なので自分がリーダーでない限りどういう規模でどういう仕事か、行くまで分からない。
D:なるほど、弦にしろブラスにしろ、セッションリーダーが居るわけだ…。
E:そうそう…。
D:それ、分かりますね。ワタシはまぁロック好きでしょ…なかでビーチボーイズがすごく好きなんだけれど、The Sid Sharp strings とあった…毎回シド・シャープさんがリーダーで録っていたってことかと。毎回同じメンツで編成していたのかな。
E:いや、オーケストラじゃないから仕事が派生した段階で誰が連絡つくかは分からないでしょう。なのでリーダーは何人も連絡先を持っていて…。
D:なるほどなるほど、ヴァイオリンにしろビオラの人にしろ頭から電話して人数分を確保すると。ということは「持ち駒」を相当数持っていないとリーダーは務まらないわけですな。
E:そうですね。
D:数はどうですか? リーダーが欲しい編成分を決める?
E:それはアレンジャーの仕事でね。6-4-2-2(第一ヴァイオリン6人/第二4人/ビオラ2人/チェロ2人)とか8-6-4-4でお願いしますってことをアレンジャーから連絡を受けてリーダーが集める…。弦パートの譜面を書くのもアレンジャーだからね。それもプロデューサーとお金の相談もした上で数を決めることだけれど…。
D:そうか、数増えればそれだけ経費が増すもんなぁ。それにしてもアレンジャーはリズムからブラスからストリングスまで…全部の楽器に精通してスコアを書くって大変だね。
E:それが仕事ですよ。
D:でもロックの現場では strings arranger/ horn arranger として専門の人間もいるよねぇ。
E:まぁそれもアリで…その場合は元々の曲のアレンジャーがラインだけを決めておいて、それをおのおののアレンジャーが膨らますんだよね。
D:演奏の段で、栄田さんがもらったスコアを弾いてみて、これちょっと変えたほうが良くなりそう…てな場合は?
E:ありますよ、たまに。時間があるときには直したりも…。
E:昔は職業アレンジャーというか、専門職の人がいっぱいいたけれど今はプロデューサーが兼ねているのがほとんど、アレンジまでやりますよね。気心の知れたストリングスやホーンセクションを使って自分の思うような音作りをする…。
D:デザインに関してもいえるかなぁ…。昔はレコード会社のデザイン室で作っていたけれど今って、どのバンドでもソロアーティストでも、デザインに携わる仲間がひとりふたりは必ずいるでしょ、だからビジュアルもバンドサイドが仕切るもんね。
E:きびしい状況ですよね。サンプリング音をいじればストリングスもブラスも打ち込めるご時世なんでスタジオがもうないですよ、どこもやっていけないから閉めちゃってる…。とくに同録で全員で一緒に録るような大きなハコはもう不要なんでね。
D:個人スタジオ作ってプロツールズ置けば、それだけで事足りる? 物事すべてがクオリティを求めていないご時世ですかねぇ。
E:mp3の圧縮音源を、いまの子らは〝圧縮された悪い音〟なんて誰も思ってないでしょう。圧縮されてない音を聴いてないんだから。
D:ストリングスというとブラスセクションなんかと比べて人数多いような印象なんだけど…。
E:そんなことないですよ。ケース・バイ・ケース、大小いろいろありです。
D:ダビング、いわゆる「後の弦の被せ」ですね…その時はどういう風に前録りの音をモニターするんですか?
E:全員が片耳にイヤフォンしてモニターしながら片方で全体と自分の音を聴いてやるんですよ。同録の場合も片耳はモニターしますけどね。
D:ストリングスは…クリック音/ドンカマ * はどうなってますか? やっぱり聴くの?
E:鳴ってるものは聴きますヨ。
D:録った音のモニターは全員でしますか?
E:だいたいやりますよ。
D:上手い下手はある…?
E:エンジニアもいろいろですよね。弦録るの初めてとか…。なかには生音知らなくて…サンプリングでしか聴いてなくて現場で初めて聴くとかね。
D:へぇ〜チェロってこんな音なんだぁ思ったより大きいですねぇ…とか (笑)? 困ったもんですなぁ。となると上手いエンジニアは際立つね。いるでしょ? 好きなエンジニアとか。戻るけどアレンジャーでもこの人は分かってるなぁなんて感じる場合も?
E:それはそうですね。やりやすいスコアを書いてくる人はいますね。
D:オレにとってはあくまでも聴くだけの話なんだけど、ロックのアルバムにおけるストリングスはすごく好きなんでね、アラバマのマッスルショールズというスタジオでの録音盤ではクライテリアというマイアミのスタジオで被せることがほとんど…それはマイク・ルイスというストリングス・アレンジャーがやっていたとか。
弦楽器というのがもともと歴史のある物で、クラシックの本場はやっぱりヨーロッパでしょう。そのためか英国ロックでの弦も好きなんですよ。ポール・バックマスター、デル・ニューマン、一番好きなのはトニー・ヴィスコンティ…まぁロックといっても裏方なんで知る人は少ないンですけどね (笑)。ヴィスコンティのストリングスというのは後で乗っけた感がないというか…エレキやベースと対等に勝負しているような〝ロック魂が入った弦〟なんですよ。まぁそんな想いがずっとあるんで、栄田さんに話を聞いてみたいなぁと思ったわけですけどね…。
E:弦に限らずだろうけど…録音している時は変だなと思っても世間に出てからイイと評価されることもあるんですヨ。逆にアクセントになって耳に残るとか…。
D:変だ変だといわれていたのがいつのまにか〝斬新〟に変わったりね (笑)。
アレンジまで頼まれる仕事の場合はスコアを書いて、自分のパートも入れるんですか?
E:弾きますよ、自分でも。
D:その時、ビオラやチェロとの響きを聴きながら…アレンジャーとプレイヤーと両方の耳を使うから大変でしょ? 書いたように音がしっかり重なっていると確認できますか?
E:ボイシング * って…ほんと大変なんですよ (笑)。服部克久さんが前に「アレンジというのはいかに音を〝ぶつけるか〟ということ」と言ってましたね。
E:昔の歌謡曲…アイドル時代はどんな曲でもバックにストリングスは欠かせなかったんですよね、レコードでもステージでも。テレビの公録にかならず付いていたでしょ。『スタ誕』とか。
D:ドリフの『全員集合』…。
E:僕見てないンですよ…福井にはネットされてなかった (笑)。
D:コントが終わって暗転…CM明けにはリズム隊と弦のパートが揃っていたんだから、ホコリっぽいよねぇ、きっと (笑)。ドタバタのすぐ後で緩やかに弦を弾くって大変だったろうなぁ (笑)。
E:昔はそれだけ仕事があったわけですよねえ。
D:今時の、ホームスタジオ派は…弦のサンプリング音を使って?
E:それでフルオケができちゃう…素人にはまったく分からない (笑)。場合によっては、サンプリングで作ったオケの一番上のラインだけ生音でなぞる…本来十数人でやるところを一人で済めばギャラもかからないでしょ…。
D:ちょろっと生音乗せかぁ、姑息だねぇそうなると (笑)。
E:そうそう…でもご時世。
D:ライヴとか、どうなんですか? 生音の必要性…。
E:ありますよ、生音が求められる現場は。
D:「ネコカル」* は? やってるんですか?
E:やってます。ただあれは遊びでね、酔っ払ってライヴやってる (笑)。弾かないとね…最近はよく練習してます。練習しないと弾けなくなっちゃうから (笑)。昔は1週間遊びに出てても戻ってすぐに弾けたけど今じゃ全然ダメ、指が動かない。
D:今日は時間を割いてもらってどうもでした。なんだか、お互いにフリーランスは食えない時代になってしまったなと寂しい締めなんですけど (笑)…まだまだやり方はいろいろありますヨ…、エール交換で終わりましょうか (笑)。
【121029 高田馬場/石庫門】