ついついマッスルまで行ってしまった姐さん。どうやらレーベルメイトにして古くからのダチ、ポール・サイモンの口ききのようで…。
 |
#082
"Joan Baez / Honest Lullaby" [ '79 CBSソニー/JP] produced by Barry Beckett <C:★> |
反体制/政治的な立ち位置が自身の想像を超えて高いところまで運ばれてしまったバエズ姐さんも70年代=内省/ある種のシラケ時代を迎えるとその立ち位置もかなり揺らいだことでしょうな。なわけで時代とのシンクロが外れてもレコードを出し続けるしかない性(さが)なればあがきながらも Keep On Singin'... 。
前作77年の『Blowin' Away』はオレのひいきのギタリスト、エリオット・ランドールがギターのみならず全面的にアレンジまで担当するという、思いもかけない「ランドール盤」であった…、Wilton Felder, Larry Knechtel, Tom Scott, Jeff Baxter, Joe Sample, Dean Parks ら売れっ子を配して狙った売れ線アルバム(…不発)からはCBS傘下 Portrait レーベル移籍、この盤はその2作目。ロス録音から目先を変えてヒット願いに誰もが目指したアラバマ詣で、マッスル録音と相成った次第。
A面がカヴァー・サイドでB面がオリジナル・サイドとはっきり色分けされた盤。しかしまあどちらもあっさり流れるというか、面白味のない盤だこと。B面はむかしながらの弾き語りに軽くバックがつく程度で曲もつまらなくハナから論外、A面のみに多少の興味を持ったが…それとても。頭はベラミー・ブラザーズの大ヒット
"Let Your Love Flow"、お次がボブ・マーリーの出世曲 "No Woman, No Cry"。ジャニス・イアン、ジャクスン・ブラウン曲が続く。
マッスルのレゲエはけっこうイケるのでどうかと思ったマーリー曲だがホーキンスのタム・ワークがまあまあぐらいで…。こちらも全体につまらない。なんの為のカヴァーなのやら、まるでカラオケで歌っているかのようで。バリー・ベケットをしてもどーにもならないバエズ姐さんで・し・た。
 |
#083
"Reuben Howell / Rings" produced by Clayton Ivey [ '74 Motown/US ] <B:★★★> |
ルーベン・ハーウェル、知らんでしょ。Nobody Know... 。オレ、意識してこの人のレコを買った初めての日本人か? そんなことないか、カントリー畑では知られてるんかなぁ?
AMGのピート項目にあったこの盤、モータウンからというのでてっきりブラックと思い込んでいたら、ド白、ディープに白い。たぶんカントリーの人。モータウンからのカントリー畑といえばシャーリーン「愛はかげろうのように」の大ヒットを思い出すところ。それは77年だったからこのルーベン盤はその前になるのだが。 クレイトン・アイヴィのプロデュースによる
Broadway Studio 録り。クレイトン/ピート/レニー・ルブラン/ロジャー・クラークのリズム隊にマッスル・ホーンズ四人衆がバックを務めるという、フィリップ・ミッチェルいうところの完璧なBチーム仕事(笑)。
最近この頁のために買う盤に多いパターン…一聴ではがっかり、その後に印象変化。これもまさにその類で、やっと見つけたレア盤ゆえ期待があったがまずはコケた。しかし2度3度と聴いてゆくうちにまあまあ悪くないかなと。とはいえこの人の本懐?カントリー調が全10曲中4曲を占めるがこれはつまらない。ほとんど同じように聴こえてオレにはいらない曲。
残りはなかなかよい選曲。Aー2"I Believe"、スティーヴィ・ワンダー作でオレはアーティ『Break Away』(参照2頁)の1曲目として聴いていた曲。次が
"You know me"、Paul Williams = Kenny Asher 作。どこかで聴いた記憶があったが分からない。AMGで見てもこの盤のための書き下ろし? Aー5"I
am what I am" はアラン・トゥーサン・ナンバー。B−2"Walkin' in the sun" も既出、傑作『I'll
be your everything』(2頁)収録のジェフ・バリー曲。B−3"You turn me around" は
Mann = Weil 作。
ここらのカヴァー(書き下ろしも?)がさすがに才能あるライターのペンによるナンバーのためにやっぱりいい。なかでもマン/ワイル・ナンバーは、オレは基本的にこのコンビ曲は金太郎飴的でおしなべるとそれほど凄く感じていなかったが中には光る曲もありということで、かなりグッときましたヨ。流石。同年のライチャス兄弟アルバムにも収録なのでそちらが本家なんだろうけど。 声の質がもろカントリーな人なのに、アランとーさん曲はシンコペ(ーション)ガンガンのお馴染みニューオリーンズ調、なのでドス効かせてハスッパな歌いっぷり…軽く笑い声まで入れてみたがどこか無理あり(笑)。ただしピートのギターが面白い。
そう、ピートに関しては全曲エレキ(アコはピートと珍しくクレイトン・アイヴィが弾く)担当なので、それなりの工夫が聴いて取れるが、いかんせん“薄い”弾きであり、“らしい”フレーズが出ないのが惜しい盤ではありました。
(040712)
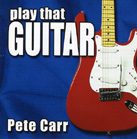 |
#084
"Pete Carr / Play That Guitar" [ '04 play that guitar media inc. PTGM1100/US ] <A:★★> |
なんとご本尊ピートの、『Multiple Flash』(4頁)以来26年ぶり3枚目のソロアルバムが完成・発売されていたのでした。80年代前半以降その名が見え難くなっていたピートゆえ半ば引退かと思っていたのだが、何の気なしに
Web Zappin' をしていたら自身のホームページ(playthatguitar.com) へと、そこにはこのCDが。なれば買わないオレではないという次第で入手。
サイトには「CD」となっているが届いてみればやっぱりな、CD−R、ジャケも一枚づつカラープリンタで刷ってみました…という、ちょっとトホホ、良く言えばヴェリィ・ハンドメイドなブツがはるばるシェフィールドから送られてきた。そう、サイトにはアドレスがないがメイリング・パッケージによれば
Play That Guitar Media の所在地はシェフィールド、アラバマ。どうやらこの会社はピートの個人事務所と思えるので、故郷フロリダへ戻っているのではと想像していたピートだが今だマッスル(シェフィールド)在のようだ。
さて全11曲うち歌は1曲のみ、残りすべてインストなのは彼のソロならお約束。その歌は "Everything
was right(A Beatles Tribute)" というその通りビートルズへのトリビュート、ビートルズ曲フレーズが満載。カヴァーが1曲、
"Oh Darlin' " というわけでピートにとっても大きな影響を受けたのがビートルズであった事実が反映された盤となった。
でもってその内容はと言えば…まあそうですヨ、そんな感じ…ったってどなたも想像できない? やっぱり当たり前に弾きまくりなのね。えーと、いい弾きまくりと悪い弾きまくりが…あるだろうか。ならばこれは、う〜んどっちつかず。ようするに歯切れが悪いわけっすよ。オレ的には。20ウン年後に聴くピートはこんなもんだろうなあとも言えるし、これなら無しでもよかったかなあとも。ヴァーサタイルなギタリスト、ピートの真骨頂と誉めることもできなくはない…とか。まあ何にしても歌伴で最高の冴えを見せるあのピート・フレーズ/ピート・リック、ソロアルバムではまったく期待してはいけないという鉄則がここでも「守られている」わけッス。
バックアップのバンドが South of the Mason Dixon Line となっていてるだけ。録音は Play That Guitar Studio。どう聴いても自宅でのいわゆる宅録ですな。サウスオブうんぬんという何人かがリズム隊を担当かと思いきや特にドラム音などは完璧に打ち込み、たたかせた生音をサンプリングしてのシーケンス作業に終始していると想像する。メカにメチャクチャ強くてその上に好きなピートなので最新機器を使いこなしているということだろうが、 Roger Clark & Lenny Le Blanc のリズム隊に Randy McCormick か Clayton Ivey あたりのキーボードという昔のメンツの演奏が聴きたかった、今もマッスルに居るならなおさら…。
見ての通りジャケに映るはストラトキャスター、でもって会社もこの赤ストラトがロゴになっている。現在のメインギターなのだろう、昔のハムバッカーびいきのピートとはこの点でも違和感あり。
そのピートサイトによれば、まあ自身なので確かだろう、いままで気づかなかった何曲かもピートがプレイしていたという。Rod Stewart "Sailin' " 、Luther Ingram "If lovin' you is wrong (I don't wanna be right)" までもそうであったとは。ならばルーサーのアルバムも探さなければ…。
*******
以下2枚、非常に関係深いブツ。両盤マッスルスタジオ録音だが同時期に、もっと言えば2枚分を一緒に録ったのかもと想像出来るほど。ともにプロデュースがブラッド・シャピロ。一枚は辛抱の甲斐があったか?…4枚目にしてやっとイケるブツに当たったミリー姐御。
 |
#085
"Millie Jackson / Free and In Love" [ '76 polydor/JP] produced by Millie Jackson & Brad Shapiro <A:★★★> |
76年のこの盤、もちろん相変わらずに感情の移入/振幅の激しさは変わらないミリーだが曲に恵まれて好盤となった、オレには。セリフ部分が他盤と較べて少ないのも救われているかなあ。曲として聴けるという意味で。
一番の曲はAー3 "Tonight I'll Shoot The Moon"。ライターが E. Struzick/S.
Storm とある。S. Storm は知らない名だがストゥラジクはレニー・ル・ブランと "Sharing The Night Together"
(see detail on page-08) を共作した人物。つまりはマッスルな人であり、ミリーがマッスル曲を歌ったという事実。非常にメロディアスな楽曲、アコギのアルペジョで飾るはピート自家薬籠中。
ピートのギターが冴えるもう1曲はB−2 "Feel Like Making Love"。日本盤ライナーでサクライという人がロバータ・フラックのナンバーとは同名異曲と書いている。しかし足らないね。この曲が
Bad Company の大ヒットだったことはロック好きにはお馴染み。畑違いかご存知なかった様子。ポール・ロジャーズとミック・ラルフスによって書かれた名曲だ。“甘いタイトルのわりにはすごくラフでロックっぽいアレンジ、ソウルファンをびっくりさせてしまいます”ともサクライさんは書いているがそりゃそうでしょ、もとがスロー・ハードロックの傑作だもの。ポール・ロジャーズといえばバドカン前に
FREE のシンガーとして知られた人物。偶然の一致だろうがマッスルとはなにかと絡むアイランドレーベルのフリー関係者の曲でピートがギターを弾いていることになる。オリジナルのラルフスに負けない粘っこい弾きまくりを聴かせてくれているのだ。
そう、いままでミリーアルバムではさっぱりだったピートのギターがここではかなり光っている。ラストの長尺 "I'm In Love Again"、ミリーお得意のストーリーテリングなナンバーだが気持ちの高揚とともに曲もスローからアップになってゆく進行、ラストまではピートも弾きまくり。オブリの冴えこそピートギターの真骨頂なのだがたまにはこれもアリですな。
マッスル曲にバドカン曲とオレ的には満足の一枚なれどソウルフリークにはちょっと違ったのかも。ライナー/サクライさんもお仕事ゆえにけなすわけにはいかずどうにか良い面を見出そうと懸命? ちなみにAー1は“フィリー・ディスコ・サウンド・イン・アラバマ”などと形容していますが、ライターは次の盤の Banks & Hampton ご両人。
recorded at Muscle Shoals Sound Studios / Musicians : B. Beckett, J. Johnson, P. Carr, R. Hawkins, D. Hood, Ken Bell, Tom Roady, H. Calloway, H. Thompson, R. Eades, C. Rose / back singers : Rhoads, Chalmers, Rhoads / Engineers : J. Masters, S. Melton / Strings Arrangement : Mike Lewis
バックメンツは完璧なマッスル仕様。4人衆にギター(ピートとケン・ベル)/パーカッション(トム・ローディ)でマッスル・ホーンズ=キャロウェイ/トンプソン/イーズ/ローズ。コーラスがローズ=チャーマーズ=ローズの3人衆。

|
#086
"Banks and Hampton / Passport to Ecstasy" [ '77 Warner Bros./US)] produced by Brad Shapiro <B:★★★> |
翌77年盤だがシャピロ仕切りで同時期に録ったと思われるマッスル盤がこれ、Homer Banks と Carl Hampton のデュオ盤。ただしこちらには詳細クレジットがなくプロデューサーと string and horns arrangement by Mike Lewis / recorded at Muscle Shoals Sound Studios とあるだけ。しかしまったくの同メンツによるセッション、つまりはピートの参加盤と見た。
ブラックは門外漢なので分からないことだらけ。たぶんコンビ組んでのファースト盤と思うがどうだろうか。この後が出たかどうか。それにこの二人があのルーサー・イングラムの名曲
"(If lovin' you is wrong) I don't want to be right" の作者であったこともつい最近知った。 前ミリー盤のサクライさんライナーにも彼らについて書かれている。曰く「バンクスは元々歌手で、スタックスに入ってからはライターとして活躍。レイモンド・ジャクソン、ベティー・クラッチーとトリオで“ウイ・スリー”としてステイプルズ、ジョニー・テイラーらのヒットを作っていた。レイモンドの死後トリオを解散、74年からカール・ハンプトンとコンビを組んでいる」。
オレ自身は10年ほど前に仕事がらみでもらったブラックのコンピCDの中の秀曲、J. Blackfoot "Taxi" のライターとしてバンクスの名を見たのが最初。といってもしばらくはバンクスはもちろんブラックフットも誰なのかまったく興味は沸かなかったが。最近になってちょいと調べてみて、ブラックフットとは70年代に
STAX で活躍した Soul Children のメンバー John Colbert なる人物であったことを知る。
"I don't want to be right" にしてもロッド・スチュアート77年『Foot Loose &
Fancy Free』収録が最初に聴いた盤というロック派のオレだが、オリジナルのイングラム盤が STAX 傘下レーベルからであること(その盤もマッスル録音でありギターはピートらしい!)、そのスタックスは南部メンフィス在のレーベル、そこからのステイプルズ始めメル&ティム
(see page-04) もマッスル録音…どうやらホーマー・バンクスも南 部を活躍の場にしていたことが今頃見えてきた次第。
とは言え、この南部マッスル産レコードは(かなり恥ずかしい)タイトルにしろジャケにしろアーバンなブラックコンテムポラリィ風情。実はJブラックフットもアナログでしっかり聴きたいと思い100円箱から件の
"Taxi" 収録盤83年『City-Slicker』を買ったりしたのだが (all songs written and
produced by Homer Banks/Chuck Brooks) 、時期もあるのかこちらはすっかり打ち込みのほぼ完全ブラコン仕様でかなりがっかりさせられた。録音はメンフィスの名門アーデント・スタジオなのだが…。
で、こちらバンクス&ハンプトン盤はマッスルリズム隊による人力録音のためにジャケほどにブラコンに毒されてはいない内容でほっとした。どっぷり甘く、女声喘ぎ声でも出てくるンじゃないかと思ったタイトル曲は爽やかなインストでありました。
いきなりの頭はチャカポコのギター・カッティング/ワウがけ、熱いアップナムバー。Aー2がそのタイトル・インストなのだがバリー・ホワイトの「愛のテーマ」から粘着質のみ抜いたって感じ。タイトなリズム・セクションが気持ちいい、とくにホーキンスのドラミングはほんとに巧い。「愛」のほうは誰だっけ?エド・グリーンあたりか?…西海岸のトップセッションメンのプレイになんら引けを取らないマッスルリズム隊、と言ってもこちらもトップだから当たり前なのだが。
残りスロー/アップの繰り返し構成。スロー・ソウルのお約束楽器、エレキ・シタールもピートが弾いております。ところで、スローな1曲B−4 "I'm
gonnna have to tell her" は5年の歳月が経っていますが "I don't want to be
right" とオールモスト「同じ」であります。柳の下のどじょうを二匹三匹と捕れるだけ捕り尽くすのが“ソウルの王道”というもの、まったくノープロブレム(笑)。そうそう、B−1は
Traffic の "Feelin' Allright" に似てますがこれはリズム隊がトラフィックのツアー(営業)から帰ってきたところでつい手が動いてしまった(特にベース)のかも…。
全体に“う〜む、このメロが来たか”という楽曲が無いのが残念。手堅い作りに終始といった印象。なおピートのギター…ケン・ベルと二人ギターだがその差が判りにくいところ、ピートらしさは少ない。
(040805)